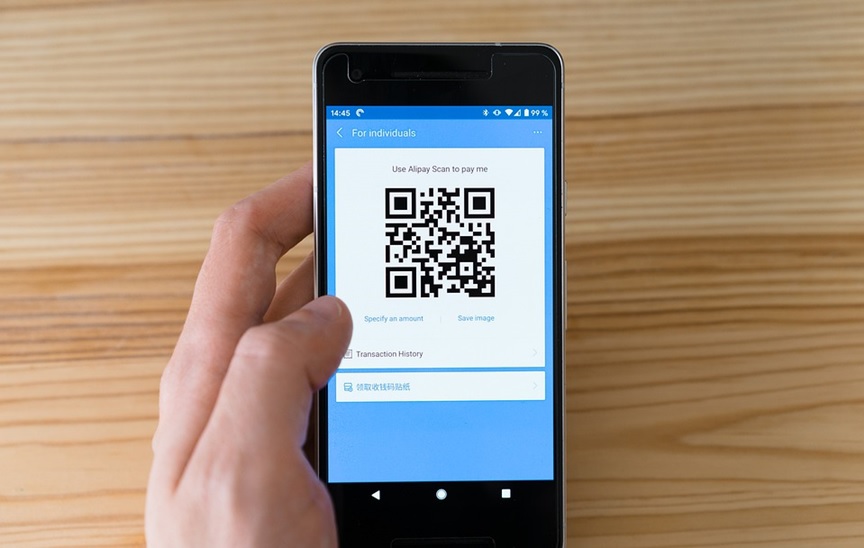33種類もあるキャッシュレス。はたしてどれが生き残るのか?
日本には今、いくつのキャッシュレスがあるかご存知ですか。
「スイカ、ワオン、アメックス、ビザ、楽天ペイ、アマゾンペイ、d払い、ペイペイ」など、これらはほんの一部で、キャッシュレスと呼ばれるサービスは今、日本銀行が把握しているものだけでも33種類あります(※1)。
しかも、33種類は銀行の自動引き落としやATMからの振込、代金引換といった伝統的なキャッシュレスを除いた数です。
ここまで増えてしまったキャッシュレスを、一般消費者はどのように理解したらよいのでしょうか。
そこで今回は、キャッシュレスを「NFC・QR・クレジットカード・プリペイド・即時引き落とし」に分類して、キャッシュレスの全体像をとらえてみます。そして、33種類もある中、どのキャッシュレスが生き残るのか?
※1:https://www.boj.or.jp/announcements/release_2018/data/rel181205a2.pdf
NFCかQRか
33種類はまず、NFC13種類とQR20種類にわけることができます。そこからQR、クレジットカード、プリペイド、即時引き落としにわかれます。
NFCに属すキャッシュレス(13種類)
日銀がNFCに分類しているキャッシュレスは次の13種類です。
●スイカ●ワオン●楽天Edy●ナナコ●iD●クイックペイ●ビザ・ウェイ・ウエーブ●アメリカンエキスプレス・コンタクトレス●JCB・コンタクトレス●マスターカード・コンタクトレス●おサイフケータイ●アップルペイ●グーグルペイ
NFCとは
NFCはNear field communicationの頭文字で、日本語に訳すと「近距離無線通信」となります。2つの機械を接近させて、無線でデータをやり取りする機能のことです。
例えば、飲食店がNFC搭載の読み取り機を持ち、客がNFC搭載のスマホを持っていれば、両者を近づけると、支払いデータを共有することができます。飲食店の読み取り機が「お金を受け取った」というデータを入手して、スマホが「お金を支払った」というデータを入手すれば、支払いが完了します。
また、鉄道駅にNFC搭載の改札機器を置き、乗車客がNFC搭載のカードを持っていれば、カードを改札機器にかざすだけで運賃を支払うことができます。カードの場合はICチップにNFCの機能を盛り込みます。
お金のやり取りのデータさえ交換できれば、あとはそのデータを使って、銀行口座にお金を入れたり、銀行口座からお金が引き落としたりすることができます。
QRに属すキャッシュレス(20種類)
日銀がQRに分類されるキャッシュレスは次の20種類です。
●はまペイ●楽天ペイ●アマゾンペイ●d払い●エポスペイ●ラインペイ●オリガミペイ●ペイB●ペイID●ペイペイ●ピクシブペイ●プリング●スキヤキペイ●スマッシュペイ●ヨカペイ●&ペイ●アクアコイン●さるぼぼコイン●しまとく通貨●シモキタコイン
日銀がこの分類を行ったのは2018年9月で、そのあとの2020年9月に、オリガミペイはサービスを終了し、事業はメルペイに吸収されました。
そして日銀は当時、メルペイをまだキャッシュレスにカウントしていませんでした。こうした激しい動きも、キャッシュレスの全体像の把握を難しくしています。
QRの仕組み:顧客読み取りと店読み取り
QRは、クイック・レスポンスという、模様タイプのコードを使ったシステムで、日本のデンソーウェーブが開発しました。
模様タイプのコードにはバーコードがありますが、QRコードはバーコードよりも多くの情報を盛り込むことができ、その上、誤読が少ないというメリットがあります。
QRキャッシュレスには、店側が提示したQRコードを顧客がスマホで読み取るユーザースキャン方式と、その逆に、顧客がスマホに提示したQRコードを店側のスキャナーで読み取るストアスキャン方式の2種類があります。
ユーザースキャン方式では、顧客が店のQRコードを読み取ることで、支払先を確定することができます。料金を入力すれば、その額のお金が顧客の銀行口座から店の銀行口座に移ります。
ストアスキャン方式では、店が顧客のスマホのQRコードを読み取ることで、受取先を確定することができます。料金を入力すれば、その額のお金が顧客の銀行口座から店の銀行口座に移るのは同じです。
QRはクレジットカード、プリペイド、即時引き落としにわかれる
QRの30種類はさらに、次の3種類にわかれます。
- クレジットカードと連係させている楽天ペイやd払いなど
- プリペイド方式になっているラインペイなど
- 即時引き落とし方式になっている、はまペイなど
この分類はとても複雑で、例えばアマゾンペイは、クレジットカードにもプリペイドにも即時引き落としにも属します。終了する前のオリガミペイは、クレジットカードと即時引き落としに属します。はまペイは、ビザ、iD、アップルペイと連動しています。
また、即時引き落としには、デビットカード方式と口座引き落としの2種類があります。
キャッシュレス事業者は利用者の利便性を高めることに熱心なので、次々と機能を増やしたり、他社サービスと連動したりしています。
キャッシュレスについては「よくわからず複数のキャッシュレスを持っているが、そのおかげで必ずどれかが使える」といった経験をしている人は少なくないはずです。キャッシュレス事業者のサービス合戦により、使えるシーンが増えているわけです。
どのキャッシュレスが生き残るのだろうか
33種類もあると、どのキャッシュレスが生き残るのか、ということに関心が集まります。例えばラインペイとペイペイは2022年4月に統合され、ペイペイが残ります(※2)。先ほど紹介したとおり、オリガミペイは消滅しています。
キャッシュレス・サバイバルは、マスコミも注目しています。マスコミ各社がどのような見解を持っているのか確認しておきます。
※2:https://www.nikkei.com/article/DGXZQODZ016LS0R00C21A3000000/
日経Xトレンドは手数料がカギを握るとみる
日本経済新聞社の雑誌、日経Xトレンドは、キャッシュレス大手5社を調査して、生き残りのカギは手数料であるとみています(※3)。手数料とは、小売店がキャッシュレス事業者に支払うお金のことです。
キャッシュレスのシステムは、消費者は無料で使うことができます。キャッシュレスはコンピュータを使ったり特別な手間がかかったりしているのに、消費者はキャッシュレスを使っても、現金の支払い額と同じ額しか支払いません。
これは、小売店側がキャッシュレスのコストを負担しているからです。手数料でコスト負担しています。
クレジットカードの場合、小売店が負担する手数料は、高い場合は売上高の7%になることもあります。しかしキャッシュレス事業者は手数料を3.25%に設定しています。
しかし、日経Xトレンドは、3.25%ではキャッシュレス事業者はコストを回収できないから、近い将来手数料を値上げするだろうとみています。そのとき、先に手数料を値上げしたキャッシュレスは、小売店に契約を解除されるかもしれません。
そうなると、資金が豊富で企業体力があるキャッシュレス事業者は値上げを踏みとどまったり、最小限の値上げでこらえたりすることができるので、生き残りやすくなります。
※3:https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/00313/00011/
スーパーアプリが勝負を左右する
金融メディアのコインチェック・ジャパンは、キャッシュレス戦国時代は、スーパーアプリが勝負を左右するとみています(※4)。
スーパーアプリとは、スマホのキャッシュレス・アプリに、さまざまなサービスが付属した「なんでもアプリ」のことです。
キャッシュレス・アプリは支払いしかできませんが、スーパーアプリになれば、タクシーを読んだり、ホテルを予約したり、ネット通販で買い物ができたりします。もちろん、タクシー代、ホテル代、買い物代は、キャッシュレス機能で支払うことができます。
支払い(決済)の便利さは、NFCやQRなどの技術によって頂点に達しようとしています。つまり決済では、キャッシュレスの優劣はつきにくくなります。
そうなってくると、今度は支払いの前段階である買い物で差をつけるしかありません。また、買い物と決済が合体すれば、決済事業のコスト(キャッシュレスの運営コスト)を買い物事業でカバーできるかもしれません。そうすれば小売店に請求する手数料を少なくすることができ、他社より有利になります。
※4:https://www.coindeskjapan.com/32975/
まとめ~実際に使いわけてみる必要がある
キャッシュレスと一口にいってもさまざまな種類があり、サービス内容や特典が異なります。種類があまりに多すぎて、頭で理解することは簡単なことではありません。
そこで賢い消費者は、複数のキャッシュレスを使って、自分のライフスタイルに合うサービスを探しています。買い物や支払いは体験そのものなので、体で複数のキャッシュレスを感じて優劣を決めることは合理的な判断方法といえるかもしれません。